どうも、ふぁいんです。
推し活も創作も関わらない理由で記事を書くのは久しぶりのような気もしますが、すごく身内な話。
父が60歳になりました。すなわち還暦です。
還暦祝いはまた改めてというところもありますが、とりあえずお祝いメッセージを送ろうと思い、色々浮かんだことを書き始めたところ、節目ということもあってメッセージで送るにしては長くなりそうな気配を感じました。
そこで、せっかくなので簡単にブログでまとめることとします。そんな記事なのでほぼほぼブログ読者の皆様には関係ない話なのですが、よろしくお願いします。
ふと思う:還暦とは
「60歳だ!還暦だ!めでたい!」は良いのですが、果たして還暦とは何だったでしょうか。
「あーあれね、あれだよね、なんか干支を一周したんだよね」
改めて問われると、これくらいのふわっとした認識である方も多いはず。……いえ、恥ずかしながら私がそうだったので、皆さんもそうだと思いたいだけなのですが、こんなときは、すっかり生活に溶け込んだChatGPT君の出番です。雑に質問してみましょう。
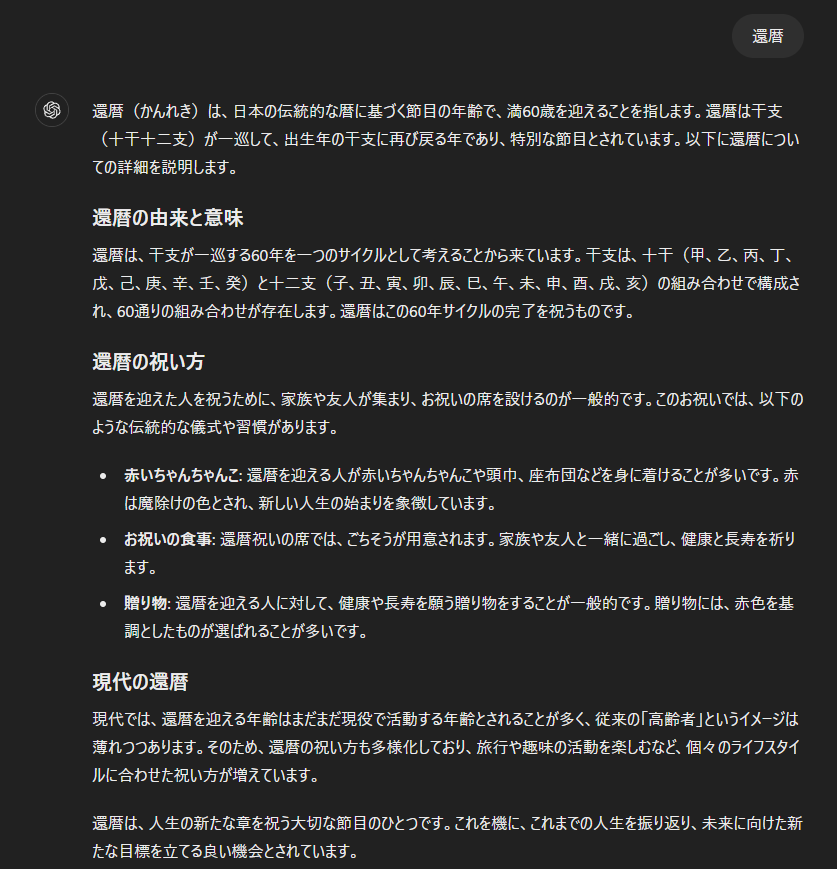
たった2文字でぶん投げたのに、完全に意図を理解して答えてくれるChatGPT君。私は無料アカウントですが、多分これはChatGPT-4o君が答えてくれました。うーん、分かりやすいですね。
画像だと見にくい方もいるかもしれないので、テキストとしても貼りましょう。
還暦(かんれき)は、日本の伝統的な暦に基づく節目の年齢で、満60歳を迎えることを指します。還暦は干支(十干十二支)が一巡して、出生年の干支に再び戻る年であり、特別な節目とされています。以下に還暦についての詳細を説明します。
還暦の由来と意味
還暦は、干支が一巡する60年を一つのサイクルとして考えることから来ています。干支は、十干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)と十二支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)の組み合わせで構成され、60通りの組み合わせが存在します。還暦はこの60年サイクルの完了を祝うものです。
還暦の祝い方
還暦を迎えた人を祝うために、家族や友人が集まり、お祝いの席を設けるのが一般的です。このお祝いでは、以下のような伝統的な儀式や習慣があります。
- 赤いちゃんちゃんこ: 還暦を迎える人が赤いちゃんちゃんこや頭巾、座布団などを身に着けることが多いです。赤は魔除けの色とされ、新しい人生の始まりを象徴しています。
- お祝いの食事: 還暦祝いの席では、ごちそうが用意されます。家族や友人と一緒に過ごし、健康と長寿を祈ります。
- 贈り物: 還暦を迎える人に対して、健康や長寿を願う贈り物をすることが一般的です。贈り物には、赤色を基調としたものが選ばれることが多いです。
現代の還暦
現代では、還暦を迎える年齢はまだまだ現役で活動する年齢とされることが多く、従来の「高齢者」というイメージは薄れつつあります。そのため、還暦の祝い方も多様化しており、旅行や趣味の活動を楽しむなど、個々のライフスタイルに合わせた祝い方が増えています。
還暦は、人生の新たな章を祝う大切な節目のひとつです。これを機に、これまでの人生を振り返り、未来に向けた新たな目標を立てる良い機会とされています。
つまり、最初にふわっと抱いていた「干支を一周した」という認識は、より正確に言うなら「干支(十干十二支)が一巡して、出生年の干支に再び戻った」ということになります。いつからこの風習があるのかは分かりませんが、昔は生まれてから幼いうちに亡くなる割合が多く、60歳まで生きるというのは、今以上に喜ばしいことだったのではないかと推測できますので、こういった節目のお祝いが生まれるのも納得ですね。
ちなみに、厚生労働省が発表する「日本人の平均余命」によれば、1964年生まれ男性の平均余命は67.67歳とされていました。それが一昨年、2022年の統計(令和4年簡易生命表の概況)では81.05歳と、13.38歳延びています。つまり、ChatGPT君も言っていますが現代の還暦は、まだまだ現役。あと20年以上生きるぞといったところですね。
今年の干支:甲辰
さて、それでは改めてですが、60年かけて1周してきた今年の干支はなんだったでしょうか。
2024年は「甲辰(きのえ・たつ)」。これについて調べていたところ、静岡県公式ホームページさんがこんな記事を書いていらっしゃったので拝借します。
今年の干支は甲辰(きのえ・たつ)です。
「甲」は鎧、草木では固い殻を意味し、その殻を破って芽を出す状況を表す象形文字です。
旧来のしきたりや慣習を破り、革新の道を進むべしという暗示です。
「辰」は、龍、竜の意味は無いようです。「農」、「震」の下の部分「あし」に表されていますが、理想に向かって辛抱強く、慎重に、抵抗や妨害と闘って歩を進める意味の表意文字です。
そして、「甲辰」の意味することは、新芽が古い殻から出るにはまだ時期が早く、なかなか出られないように、旧体制を打破するには抵抗や妨害があり、それらと闘う努力をし、着実に慎重に遂行すべしということを示しているようです。
第13回『今年の干支(令和6年・2024年)』 静岡県公式ホームページ https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/v_governor/1001838/1046815/1059621.html
これを読んで、なんとなく納得してしまった自分がいました。
1964年と言えば、初めて東京でオリンピックが開催された年であり、高度経済成長期のただ中という認識です。ある意味で、革新の第一歩だったと言えるでしょう。
そしてそこからの60年は、バブル期があり、情報革命、IT革命があり、そしてこの令和には、さきほど助けてくれたChatGPT君を皮切りに、AIが実用レベルで生活に浸透してきました。
そう思うと、なんと激動の時代なのでしょう。無論、情報革命やAI出現などは私自身もこの身で体験してきていることではありますが、経済も、技術も、変わりに変わり、そしてまさに今、日本は「Japan as No.1」からの栄枯盛衰を経て、半導体などの分野で巻き返しを図ろうとしているというのですから、本当に時代の先を読むのは難しいものです。
もし今バブル期に戻り、日本の競争力低下を伝えたところで、誰も信じないでしょうね。
混乱の時代
さて話を戻しますが、そんな激動の時代、その背景には、旧態依然とした慣習や価値観との衝突、あるいは「新しいがゆえの不理解」があったことでしょう。私は、昨年話題となった映画『Winny』を思い出してしまいました(ついこの間Amazon Primeで見たからというのもある)。
あの映画では、「新しい技術」が危険視されたがゆえに、後世から見れば「もったいない」と言わざるを得ない損失を生んだという部分が注目されました(詳しくは映画を見るかWikipedia「Winny事件」をどうぞ)。
実際、私も映画を見てそう思いましたし、あの頃、Winnyに使われた技術をいち早く伸ばしていれば、IT時代の勝者は日本だったのではとも思いました。しかしそれはあくまで「後世から見れば」なのです。あの頃、あの時代に、大衆にそれを理解させるというのは難しかったのだと思います。あれは、Winny、そしてP2Pという新技術が生んだ「混乱」でした。
それも踏まえて私は、この60年は、――いや、あるいはいつの世もそうなのかもしれませんが、激しすぎる世の変遷に混乱し、熱狂し、振り回され続けた60年だったのではないかと思うのです。そんな世の中を、さて、我が父は何を感じながら生きてきたのでしょうか。
父親を一言で表すなら
私から見える父親は、……改めて表現しようとすると難しいのですが、一言で表せと言うのであれば「苦労人」なのかなと思います。私が生まれて以来ずっと「失われた30年」ですから、そのせいもあるかもしれませんが、「今勢いに乗ってるぜいけいけ!!」みたいな雰囲気を感じたことがありません……文字にするとちょっぴり悲壮感が出てしまいますね笑
とはいえ別に、家庭内が暗く沈んでいたということは一切なく、なんなら子供の身からすれば、やりたいことはやりながら過ごしてこられたと思っていますし、苦労はありませんでした。おそらくその分の苦労を、親として、無論母親とも分担しながら、背負ってくれていたのだと思っています。
今だから実感を込めて思うことですが、私を含め子供3人、大学、短大まで卒業させて育てきることのなんと大変なことでしょう。現在独身で、なんならひとりを謳歌しすぎている私からすると、うーん、だいぶしんどいかもしれない、というのが正直なところです。
ただ、そうは思いつつもどこかで「まあ、いざとなったら何とかなるんだろうな」と思っているのは、実際に何とかしてきた父を見ているからというのが大きいところでしょう。
「大変でも辛抱強く、日々を生き抜くために知恵を絞る」
そんな背中を見てきたつもりなので、そこから感じ、形成された人格があるのだろうなと思います。
アウトプットの集大成をよろしくって話
さてここまで読んできた家族以外のもの好きがいれば、
「家族のために苦労してきたお父さんなんだなあ」
と、思われるかもしれません。
実際それはそのとおりではあるのですが、ひとつ言っておきたいのは、先ほども述べたとおり、「別に暗い雰囲気はなかった」ということです。ここまでの書き方だと何となく、「寡黙で、背中で語る昭和の父」みたいなイメージに寄っていきそうなのですが、どちらかというと我が父は、「よく語り、よく書き、直接伝えるおしゃべりな父」です笑
なんなら母や妹たちからは少々ウザがられているところもあるくらいには、自分の考えを持ち、アウトプットする父だと思います。結果、必然的にアウトプット先が息子である私に向きがちだったので色々話を聞いてきましたが、それもまた、私自身の人格形成に多大な影響を与えてきました。なんならこうして、「父の還暦」にかこつけて長々とアウトプットをしてしまうような人間に育ったのは、父のせいということもあるでしょう笑
我が父は、よくメモを残しているイメージがあります。また、その年の目標や考えなどもきちんと表明し、自らの指針にする、といった印象もあります。その目標の中には「新しいこと」が盛り込まれることも多く、その時々で常に「興味のあること」や「必要なこと」を見つけて挑戦していく……そんなイメージです。その振り返りをどうやってしているのかまでは把握していないのですが、きっといつも通り手書きで何かをアウトプットしているのでしょう。そう考えると、アナログかデジタルかの違いはあれど、私も全く同じことをしているので「あー息子」という感じです笑
(このブログにおける年末年始振り返りや誕生日振り返りなどはまさにそう。はたまた毎週のラジオで、興味や思考をアウトプットするのもそうかもですね)
一番似ていると思うのは、それを「楽しもうとする心」だと思っています。私の座右の銘は「おもしろく生きる」ですが、父も日々の言動を見るに、挑戦を楽しもうとしているんだろうなと思っています。それはある意味、働くばかりの毎日で消耗するだけにならないようにというところもあったのかもしれませんが、そうして前向きであったからこそ、我々子供達に苦労が伝播することなく、ここまでこれたのかなという気がしています。
そうなると気になるのは、還暦を迎えた父がこれからどこを向き、何を楽しもうとしているのかというところです。その一方で今回の記事タイトルにしましたが、そろそろ、少しずつ自分のこれまでをまとめておいてくれてもいいなあと思っています。「この60年は激動だった」と書いたように、間違いなく後世の教科書に載るだろう時代ですから、シンプルにどう感じて生きてきたのかが気になりますからね。とはいえそこまで無茶ぶりでもなく、色々アウトプットしてきたこれまでの記録もありそうなので、まあ書けるんじゃなかろうか、と勝手に見積もっています。少なくとも母はそんなことをする人ではないと思うので、やるなら父しかいないでしょう笑
まだまだ元気に過ごせる今だからこそ、新プロジェクトとして着手しておいてほしいですね。
私はいずれ遺産として、(勝手に)父から星新一の単行本全てを相続するつもりなのですが、そのときに父の自伝も添えてくれたら非常に面白いなあと思います笑
以上、思ったより長くなったので記事にして正解だったと思ったふぁいんさんでした。
誕生日おめでとうございます。
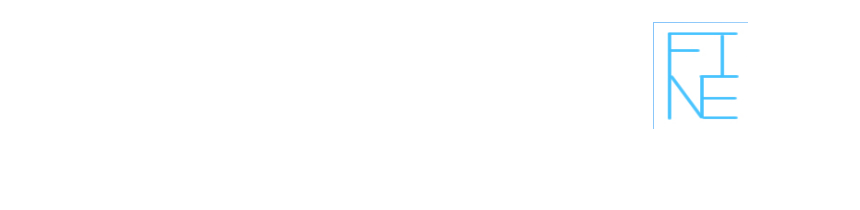




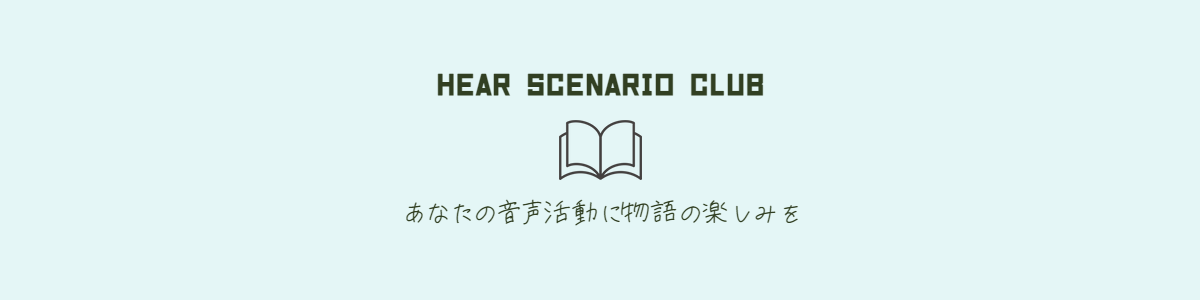
コメント